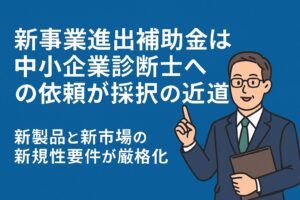アジアでの食品販売チャネル開発

9月6日と7日にインテックス大阪で行われましたフードストアソリューションズフェアの展示会に、顧問先企業のブース出展のお手伝いをしました。
この展示会は大手のスーパーマーケット等の小売業や卸売事業向けに、小規模の地域食品企業が販路開発を目指し約400社以上が出展しています。いわゆる大手食品製造会社でなく地域特産品の特徴ある食品を展示訴求されており、中小食品メーカーと流通販売チャネルを開発し、スーパーや卸事業者にとっては、売れる商品を発掘するための出会いです。
食品業界は、部品加工などの製造業のように小ロットカスタム品対応や量産品対応というよりも、あくまで小売店の販売最先端で消費者に買っていただくための味や商品アピールの価値であるとか、需要が当たったときの量産や価格の柔軟性など、同じ製造業でも全く流通体系が異なります。
元々、電機業界出身なので、現在支援している食品の卸売事業とは感覚が異なる部分があるのですが、マーケティングという点では共通項もあり勉強することも多いです。
小規模ゆえ海外需要に対応する術をしらないところが多い
400社余りの出展企業をつぶさに見たわけではないですが、9割以上のほとんどの出展企業は海外市場には全く関わっておられません。ただやり方によっては十分海外でも売れそうな商品がたくさんありました。ところが実際には海外にどう取り組んで良いのか全くわからないという状況かと思います。
一部輸出したことがあると言われる事業者もありましたが、輸出商社からの引き合いで出しただけで、実際に現地に出かけて市場を調査したこともないというところがほとんどでした。
うまく伴走支援者と共同で取組めば十分に海外市場での販路開拓の望みがあると感じた展示会でした。
海外市場開発のやり方は国内の販路開拓と大きな違いはない
国によっては流通形態も異なるので全世界共通の販路開拓の手法というものではありませんが、事例としてアジアの食品市場の一つであるベトナムに向けて取り組みたいというところがあれば、だいだい下記のような観点から支援します。ほぼ国内の販路開発とは大きな違いではないと思います。
【1】伝統的チャネル(Traditional Trade)
■ 小規模個人商店(ティエウ・トゥー:Tạp hóa)
- 地域密着型で、住宅街や路地に多数存在。
- 食品・日用品を少量単位で販売。
- 信頼関係や掛売りが重要な購買要因。
- 地方や農村部では現在も主流。
■ ウェットマーケット(Chợ)
- 生鮮食品(肉・魚・野菜・果物)が中心。
- 価格交渉や現金取引が一般的。
- 朝~午前中が営業のピーク。
- 安価で新鮮な商品を求める層に人気。
【2】近代的チャネル(Modern Trade)
■ スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- 例:Co.opmart、Big C、Lotte Mart、Aeon、Mega Market(旧Metro)
- 品質管理が徹底されており、中間~高所得層が主な顧客。
- 食品表示、包装、衛生面など日本と近い基準が求められる。
- 輸入食品やオーガニック商品なども多く取り扱う。
■ コンビニエンスストア(CVS)
- 例:Circle K、FamilyMart、Ministop、Winmart+
- 都市部・若者・単身者をターゲット。
- 軽食、飲料、スナック類の販売が中心。
- 24時間営業やキャッシュレス対応など利便性重視。
■ ショッピングモール内の食品専門店
- 高品質・輸入志向の食品を扱う。
- 富裕層や外国人顧客を意識した品揃え。
【3】Eコマース/オンライン販売
- 急成長中。特にコロナ禍を契機に需要拡大。
- 主要プラットフォーム:
- Shopee、Lazada、Tiki、Tiktok Shop
- GrabMart、BAEMIN Mart(食品デリバリーと連携)
- 冷凍・加工食品、スナック、飲料などが人気。
- 若年層・都市部住民を中心に浸透。
- 自社ECサイトやSNS販売(Facebook/Instagram)も重要。
【4】業務用(B2B)チャネル
- レストラン、カフェ、ホテル(HORECA)向け。
- 食材供給業者、業務卸が中間に入る。
- 日本食材の需要も高まっており、現地商社や日系卸業者が介在。
実際にはターゲット市場と流通チャネルの調査を現地出張して、目と肌で感じてもらうところから全てが始まると思います。商社任せで価格と納期だけで販路開拓できるほど簡単ではありませんし、これは日本で新たに取引先を広げていく手法と何ら変わるところはないでしょう。
ご相談があればお気軽に。