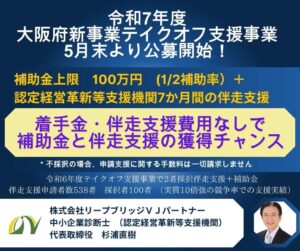不易と流行

松下幸之助の経営哲学に「不易と流行」という言葉があります。社会人になったばかりのころ、経営研修でこの意味について教えられたのですが、当時は自分のこととしても意味がわからず、会社経営の考え方としても自分事ではなく、偉いさんだけがわかっているだけで十分かと思っていました。
ただ、仕事を覚えるつれ、経営の本質について経験を積みかさねていくようになると、会社経営とは変えるべきことと、変えてはいけないことの考え方について軸がぶれると大変なことになるということがだんだんとわかってきました。
しかも、変えてはいけない「不易」と環境に変化に柔軟に対応していくべき「流行」は、会社経営に留まらず、国が発展するも衰退する点でも極めて重要であると思うようになりました。
松下幸之助翁は、経営は変化する時代に合わせて変えるべきものと、絶対に変えてはならないものがあることを示唆していました。特に変えてはならないのは、企業の経営理念や経営者の哲学など、会社、従業員、社会にとって何が正しいのかという根本的な価値観です。この軸をぶらすことなく、時代に合わせて環境の変化に対応していくことが経営の根幹であるとの考え方を繰り返し話していました。具体的には、
「変えるべきもの」:経営環境の変化に合わせて、ビジネスモデル、商品・サービス、経営構造、経営戦略などの柔軟かつ素早い変化対応です。時代や状況に合わせた「流行」変化こそが企業を成長させるために不可欠です。
「変えてはならないもの」:企業の経営理念、従業員への思い、社会への貢献、企業の根幹となる価値観は、どんな時代であっても変えてはならないという考え方です。松下幸之助翁は、これらの価値観を「不易」と定義していました。
経営者としては、何でもかんでも前任者を否定して「流行」を追い求めるのではなく、変えてはならない「不易」を堅持する信念とのバランスを見極める力こそが経営者たる所以であって、企業を成長発展させていく必要があると説いていました。まさしく素晴らしい経営者かどうかはこの点を見てみればわかるように思います。
国家運営においても不易と流行は重要
昨今の国際情勢の混沌化の中で先行きの不透明感が強まり、日本の政治も経済もどんどん劣化しているように感じます。ところが、今の日本国家の経営だけでなく日本国民の考え方についても「不易と流行」という視点は非常に重要であると気づくことが多いです。
少子化が加速し国力が衰退していく中で、政府や政治家は国家運営のための収入つまりいかにして国民から税金として吸い上げて財源を確保するかに汲々としています。政治家や官僚にとっては「変えてはならない不易」との価値観で国家運営しています。しかしこれは明らかに間違いです。民主主義国家においては、本来は国の役割は極力国民の安全、安心を保障することであって、それ以外の富の再配分の役割をできる限り削減し、そのための予算は縮小させて減税による成長投資に向けさせるべきものです。めたらやったら補助金ばかり肥大化させて、国の事業を生み出すことが社会発展に貢献するというのは明らかに官僚や政治家の驕りのように思います。国の政策でお金を配ることは極力手控えないと、官僚組織はどんどん水膨れし財源はいくらあっても足りません。
政府役人や政治家は、お金をどう配るかといった環境の変化に迅速に対応するための政策は、本来は「流行」の考え方に立つべきであって、決して「侵さざるべき不易」という考え方は捨て去ることが最も重要だと思います。
むしろ国家として変えてはいけない国家の根幹となる理念を「不易」として国民的合意を図ることがより大切な気がします。ところが国民においても、「不易」と「流行」を取り違えている人が特にリベラル系に相当多いように思います。
憲法を一切変えてはいけない「不易」の理念のように言う人がいますが、私は法律というものは、国民の生命財産を守り安全安心を保障するために存在意義があるのですから、憲法も含めて時代の変化に合わせて変化させる「流行」の考え方に立つべきものだと思っています。
それよりも大切なものは「変えてはいけないのは国家としての、また国民としての価値観」であると思うのです。国は国民があって成り立つものであって、それが民主主義の根幹です。つまり日本という国の存在は日本国民を統合する枠組みであって、その枠組みの中に価値観として家族制度があって日本国民の戸籍制度が存在しているのです。
私自身はどちらかというとリベラルの考え方にはあまり共感できません。少子化の中で外国人労働者の受け入れは致し方ないところですが、かといって無暗に移民を認めたり、帰化を甘くすることで、社会統合の課題や外国人に対する経済負担の増加、治安の悪化、文化の喪失など、日本国民が犠牲になって、国民統合のしくみやルールが崩壊しているように誘導しているようにしか思えません。LGBTについても選択的夫婦別姓についても、単に不便だからとか人権問題だからといった流行の視点で誘導するのではなく、皇室制度も含めて日本国の存在価値に触れる「不易」の考え方に立つべきなのが、リベラルの対局側にいる保守層の国家理念だと思っています。
私も現役時代は多くの国で働いてきました。しかし、常にその国の文化や社会の考え方を尊重し、あくまで受け入れてくれた国や人々に迷惑をかけず、どうすれば貢献できるかということを考えて暮らしていました。アメリカでは子供たちの教育でも大変お世話になり大変感謝しています。どうやったらその恩返しができるか常々考えていましたし、極力日本人が集中して住んでいる地域から離れて、アメリカ人と交じり合える地域で住んでいました。
今日本で起きている外国人との軋轢の多くは、同じ国の人だけでコミュニティを形成し、日本人の価値観や社会のルールを無視し、税金も払わないで医療費を踏み倒し、自分の国で土地を買えないのに、日本で土地を買いあさって、民泊経営という経営者としてビザを取得し、事実上家族を呼び寄せて移民化しているということで、日本人の価値観が壊されていくことへの恐れと怒りが頂点に達しつつあり、それが政府や政治家不信につながっていくように思えるのです。
官僚も政治家もそして国民一人ひとりが、今一度日本人としての「不易と流行」を改めて考えるべきときではないでしょうか。