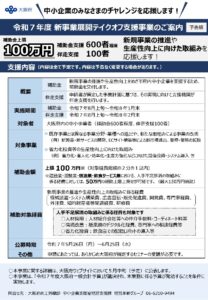トランプ相互関税とASEAN事業戦略の立ち位置

トランプ米国大統領が打ち出した相互関税の衝撃は、日本企業のみならず世界貿易のあり方を根本から問い直しています。世界各国の企業は、米中の貿易摩擦や中国国内の経済危機が及ぼす事業リスクを最小化するため、サプライチェーンの強靭化とビジネスモデルの再構築に取り組んでいました。
中国企業自身も中国製品を米国に輸出する際の関税リスクを下げるために、近年では怒涛のごとくタイやベトナムなど東南アジアに製造拠点を設立、もしくは地場資本と合弁事業を加速していました。いわゆる中国企業が東南アジアを経由して米国への迂回輸出拠点としての事業戦略を推進していたわけです。
ところが今回のトランプ相互関税では、中国の迂回輸出拠点として東南アジア各国に対し、日本や韓国などよりも高関税を課すると発表された印象です。タイやベトナムなどASEAN各国の政府も大混乱し、米国からの輸入品に対する関税をゼロにすると発表するなど躍起になって動いていますが、本日の問題は中国にあるにもかかわらず、その中国との距離をどうするかという視点が欠けている以上、かなり厳しい状況になるのではないかとみています。
その点で日本企業の海外事業戦略支援や、ASEAN各国の動きに深く関与してきた立場から、今回のトランプ関税の本質と、日本政府やASEAN各国政府が90日間の猶予期間に取るべき対応策について、中国:ASEAN:日本と米国の軸で考察してみたいと思います。
問題の本質は中国にある
一見、今回のトランプによる相互関税は暴挙と見られがちですが、米国の認識としては、中国に対する堪忍袋の緒が切れたというのが実態です。中国は2001年にWTOに加盟が認められました。その加盟にあたっては不公正な貿易を続ける中国を世界の貿易機関に取り組み、ルールを守らせることで世界経済全体の発展に寄与させるという目的もあり、むしろ米国が全体を主導して実現したと言われています。
ところが中国は国家戦略でWTOをコントロールし始める一方、自国の都合の悪いことは一切無視したため、結果的にWTOを機能不全に陥らせてしまいました。米国が最も頭にきているのが、①外資に合弁を条件に中国投資させて先端技術の移転を条件にすることで知財や技術を不当に盗み放題にしたこと、②国が戦略的分野に巨額の補助金を注ぎ込み不当に安い価格でダンピング輸出を行い続けていること、③中国はASEANなど高関税の国に投資または迂回して米国に輸出することで、圧倒的な貿易不均衡を増大させることで米国の国内産業を衰退させてきた、という点です。
米国は中国人がメンツにこだわることは既に見抜いており、絶対に報復関税をかけてくるとわかっていました。中国以外の欧州やアジア各国が状況を把握し、どのような動きをするべきか考えあぐねている間に、中国だけがまんまと罠に引っかかり、90日の猶予なしに145%の輸入関税がかけられることになってしまいました。
今後はどのような国家間の駆け引きがあるかどうか予断を許しませんが、中国を除く他の国はどのような対応策を取るべきか自分なりの考えをまとめてみました。
日本を含めアジア各国は中国との距離感を慎重に
日本に対する相互関税率は24%で上へ下への大騒ぎですが、一方アジア各国でも、カンボジア49%、ラオス48%、ベトナム46%、ミャンマー44%、タイ36%と軒並み日本より高い関税をかけられています。
これは中国で製造された半製品や部品がASEAN諸国に輸出されてで軽微な加工を行い、ASEAN諸国を原産地として米国へ輸出される「原産地偽装」拠点として認識しており、特にベトナムやカンボジアからの輸入品に中国製部品が含まれる割合が高いとの指摘するように迂回路国の存在は、トランプ第一次政権が目指した対中関税の効果を弱め、米国の貿易赤字削減につながらなかったとしています。
相互関税が発表され、ベトナム政府もすぐに動きました。ベトナムへの輸入関税の引き下げ検討とか、二国間貿易協定交渉の加速などあたふたしている様子が伺えます。ただ、一番忘れてならないのは中国との関係の見直しです。ベトナムにとって最大の輸入国は中国で全体の34%である一方、最大の輸出国は米国で全体の27%です。双方とも第二位を圧倒的に引き離しています。つまり今のベトナムの産業構造は、中国から半製品や日用品を輸入して、完成品にして米国輸出で黒字化できているといえます。

米国からの輸入は全体の4.2%しかないのですから、この輸入関税をゼロにすることは米国にとっては貿易交渉の材料にはなりえません。狙いは中国排除であることを真剣に受け止め、どれだけ中国依存から貿易構造を変えていくのかという戦略の方向性を、ベトナムに限らずASEAN各国は考えていくべきかと思います。
さらに、要注意な点があります。それは中国自身のアジア各国に対する圧力と同時に、アジア各国が今中国にどのような対応をしているのか米国がよく見ていることです。日本のバカな政府与党は、事態が流動的であるにもかかわらず、この時期に中国を訪問しして協議しようとしています。今は、米国とのコミュニケーションを密にする努力の時期であって、対中国ではじっとしておくべきです。困ったものです。
おそらく中国はASEAN各国や日本を味方につけて米国を何とか孤立させようと動くことが想定されます。それはアジア各国にとっては最悪の結果を招く恐れがあります。あらゆる世界経済の問題の根幹が中国にあることを認識すれば、今何をなすべきか、また何をしないべきか考える必要があります。
TTPとEUの経済連携の重要性
突出した米国関税をかけられた中国は、手を変え品を変え、アジアや欧州、中南米を利用した迂回輸出対策をしてくるものと思いますし、過剰生産の行き場を失った中国製品は、ダンピング輸出で世界各国の産業をさらに疲弊させてくるものと思われます。
対米国交渉だけでなく対中国戦略の点においても、米中以外の経済協定圏で相互連携を行うことがさらに重要となってくるものと思います。中国は今までASEANでの製品加工プロセスをサプライチエーンに入れることで対中高関税を回避してきました。ところが今回アジア各国に高い相互関税をかけられたとは言え、145%の中国から見ると大差がついてしまったことで、おそらく迂回輸出のルート開発はしてくるものと思われます。特に、シンガポールでのオペレーションが要注意です。シンガポールの関税率が10%にとどまったことを考えますと、中国に限らずアジア各国やインドまで何とかシンガポールからの輸出を目論んでくるでしょう。またマレーシアは24%です。高関税のカンボジアやベトナムにとって、何とかマレーシアやシンガポールでの付加価値基準を組み入れて原産地戦略を考える方法や、思い切ってイギリスの10%を適用するような貿易モデルも検討もできるのではないでしょうか。
しかし、このあたりは米国は注視していますので、一つ間違えると新たな追加関税が発令される可能性もあります。
それらの状況を考えますと、米国も中国もメンバーでなく、主要ASEAN各国やカナダ、メキシコ、チリが締結国であるTTPとEUが今こそ経済連携を進めることが重要かつ米中問題のリスク軽減に資するものと考えます。
いろいろな選択肢がでてきます
関税はあくまで製品の輸入時にかけられます。つまり一般的にサービス取引は関税の対象外であるということです。最近の商品価格は、製品価格だけでなくサービス対価として保守メンテナンスなどを別契約にして決められることが増えています。極端かも知れませんが、製品本体価格を極小化し、ソフトパッケージを別売りにしてそこで付加価値部分として販売する事業モデルも検討できるのではないでしょうか。
米国もことさら貿易赤字が巨額だと強調していますが、一方で金融事業やIT、ソフトウェアなどでは大幅な経常黒字になっているので、決して米国だけが貧困化しているわけではありません。実際、皆さんが使っているマイクロソフトのOfficeに高額のサブスク使用料を払っていますが、マイクロソフトのソフトダウンロードで関税を払っているわけではないので理不尽であることは間違いありません。
実際、米国はスマホや半導体製造装置などの電子関連製品や医薬品、エネルギー及びエネルギー産品、特定の重要鉱物資源も相互関税対象外にする動きも出てきていますし、今後産業界からの強い要望によって、追加関税免除の品目が増えてくることは十分に予測されます。今後の選択肢については、短期的判断で慌てた動きはしないのが賢明でしょう。